昭和の名ビル&レトロ銭湯を巡る1日密着SP
今回の「サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん」は、「昭和の名ビル」と「レトロ銭湯」をテーマに、博士ちゃんたちが貴重な建築物や文化を巡る特別企画。六本木エリアの再開発が進む中、今のうちに見ておきたい昭和・平成の名ビルを航空写真博士が徹底調査。また、東京都内で最も銭湯が密集している大田区で、銭湯好きの博士ちゃんがレトロ銭湯を巡り、その魅力を紹介しました。懐かしい昭和の風景と、今も残る銭湯文化に触れる特別な1日をたっぷりお届けします。
航空写真博士が巡る!六本木の昭和・平成の名ビル探索
東京都心の中でも特に開発が進んでいる六本木エリア。再開発ラッシュが続くなかで、多くの昭和・平成の名建築が消えつつあります。今回は、航空写真博士の陽心くんが、貴重な建築物を巡り、昭和から平成にかけての六本木の歴史を探りました。同行したのは、六本木の移り変わりをよく知る山田邦子さん。彼女の思い出話とともに、かつての六本木の姿を振り返ります。
- 六本木のシンボル「アマンド 六本木店」
六本木交差点にある老舗カフェ「アマンド 六本木店」は、昭和・平成を通じて多くの人々の待ち合わせ場所として親しまれてきました。1990年代には店頭にシェードがあり、雨の日でも安心して待ち合わせができたというエピソードも。かつて六本木で遊ぶ人々が立ち寄る定番スポットであり、時代とともに変わりゆく六本木の象徴でもあります。
陽心くんは、山田邦子さんから差し入れされたアマンド名物の「リングシュー」を路上で味わいながら、六本木の懐かしい雰囲気に思いを馳せました。このリングシューは、昔ながらのカスタードクリームがたっぷり詰まった一品で、アマンドが愛され続ける理由のひとつです。 - 昭和のグルメビル「瀬里奈ビル」
次に訪れたのは、六本木駅から徒歩3分の「瀬里奈ビル」。高級レストランが集まるこのビルには、「瀬里奈本店」や「六本木モンシェルトントン」などの名店が並びます。昭和の時代から美食の街・六本木を象徴するスポットであり、当時の贅沢な食文化を支えてきました。
山田邦子さんは、ここで「初めてブランド肉を食べた」と振り返り、その味の衝撃を語りました。特に瀬里奈本店は、神戸ビーフや黒毛和牛のすき焼き・しゃぶしゃぶが楽しめる名店として知られています。 - バブル期を象徴する「ジュールA」
続いて訪れたのは、麻布十番に建つバブル期の象徴「ジュールA」。このビルは、当初会員制レストランやクラブが入る高級施設としてオープンしましたが、現在はオフィスや飲食店、住居を兼ねた駅直結の複合ビルとなっています。
特徴的なのは、外壁に施された「雲のデザイン」。これは単なる装飾ではなく、視界を遮ることでプライバシーを守る役割を果たし、さらに幹線道路の騒音を防ぐ効果もあるという機能美を兼ね備えたデザインです。バブル時代ならではの贅沢な建築様式が伺えます。 - 偶然発見!昭和49年の丸窓エレベーター付きマンション
街を歩いていると、ひときわ目を引く建物を発見。昭和49年に建てられたエレベーター付きマンションで、最大の特徴は丸窓が付いたエレベーター。当時のマンションとしては斬新なデザインで、モダンな雰囲気を醸し出しています。
昭和の時代には、エレベーターに丸窓をつけることで開放感を演出し、圧迫感を軽減する工夫がされていたと言われています。今ではなかなか見かけないレトロなデザインが、当時の建築トレンドを感じさせます。 - 白井晟一設計「ノアビル」の独創的な美しさ
次に向かったのは、民間企業やフィジー共和国の大使館が入る「ノアビル」。昭和49年に建設されたこのビルは、当時まだ高層ビルが少なかった中で異彩を放つ建築物でした。
設計を手がけたのは、日本のモダン建築を代表する建築家白井晟一。彼の代表作として知られるこのビルは、下層部がレンガ造り、上層部が銅板で仕上げられたユニークなデザインが特徴です。特に銅板は、年月とともに味わい深い色に変化するため、経年変化を楽しめる建築として高く評価されています。 - 東京タワーから眺める六本木の変遷
最後に訪れたのは、六本木エリアを一望できる東京タワー。
かつては、六本木ヒルズも東京ミッドタウンも存在しなかった時代がありました。しかし、昭和から平成、そして令和へと時代が進むにつれ、街の景色は大きく変貌していきました。
・昭和40年代前半までは、六本木に都電が走っていた
・六本木は戦前、陸軍の街として発展し、戦後は米軍が進駐し「東京租界」と呼ばれるエリアだった
・昭和から平成にかけて、バブル期の影響で高級クラブやレストランが急増
・六本木ヒルズ(2003年開業)と東京ミッドタウン(2007年開業)の登場により、再開発の象徴的なエリアへと変貌
こうした歴史を知ると、現在の六本木の景色もまた違った見え方をするかもしれません。今後、さらなる再開発が進むことで、六本木の街並みはさらに変わっていくことが予想されます。
陽心くんの調査を通して、消えゆく昭和・平成の名ビルの価値を再認識することができました。今のうちに、その歴史的な姿をしっかりと記録しておくことの大切さを改めて感じる時間となりました。
レトロ銭湯博士が行く!東京No.1密集エリア・大田区の銭湯巡り
東京都内で最も銭湯が多い大田区。今回は銭湯博士のふじおくんが、銭湯好きの澤部佑さん(ハライチ)と共に、大田区にある歴史ある銭湯を巡りました。ふじおくんは、全国浴場新聞にも掲載された銭湯マニアで、銭湯の歴史やルールに精通しています。
- 大田区には現在33軒の銭湯があり、都内最多の密集エリア
- 「黒湯」という独特の温泉が湧き出るエリアで、湯冷めしにくいのが特徴
- 昔ながらの番台が残る銭湯や、今も薪でお湯を沸かす銭湯など、個性的な施設が多数
今回は、そんな大田区のレトロ銭湯を代表する3軒を巡りました。
蒲田温泉で黒湯を堪能
最初に訪れたのは「蒲田温泉」。ふじおくんは、銭湯に入る際のこだわりとして、いつも「123番の下駄箱」を使うと話しました。番号の選び方には個人のこだわりがあるそうで、これは銭湯マニアならではの視点です。
- 鍵は失くさないよう、肩まで上げて持つのがポイント
- 湯船に入る前に全身を洗うのが銭湯のマナー
蒲田温泉の最大の特徴は、関東特有の「黒湯」。この黒湯は、海藻や植物が長い年月をかけて分解されることで生まれるフミン酸を含み、湯冷めしにくく、美肌効果があると言われています。
また、お風呂上がりには定番の「コーヒー牛乳」を飲み、昭和の銭湯文化を存分に味わいました。
- 銭湯の定番といえば、風呂上がりの飲み物
- コーヒー牛乳、フルーツ牛乳、瓶の牛乳など、銭湯ごとにこだわりがある
- 蒲田温泉の自販機には、瓶入りのレトロな飲料が並んでいる
薪で湯を沸かす「大正湯」
次に訪れたのは、昔ながらの薪でお湯を沸かす「大正湯」。都内ではガスや電気を使う銭湯が主流となっていますが、ここでは今も薪を使ってお湯を沸かす昔ながらのスタイルを守っています。
- 薪でお湯を沸かすことで、お湯がまろやかになり、肌当たりが優しい
- お風呂の温度が絶妙に調整されていて、湯冷めしにくい
また、大正湯では銭湯の壁画を描く絵師が定期的に壁画を描き直しています。現在、都内で銭湯の壁画を描く職人はわずか3人。その一人である田中みずきさんが、大正湯の壁画を手がけています。
- 壁画の代表的なモチーフは「富士山」
- 銭湯といえば富士山の壁画が定番
- 大正湯では、定期的に壁画を描き直し、新しいデザインを取り入れている
ふじおくんは、関西の銭湯との違いについても解説しました。
- 関西では、円形の湯船をカラン(蛇口)が囲むデザインが多い
- 関東では、こうしたデザインはほとんど見られない
関東と関西で異なる銭湯文化を比較しながら、それぞれの魅力を楽しみました。
〆のグルメが楽しめる「桜館」
銭湯巡りの最後に訪れたのは、「桜館」。ここは、銭湯ながら露天風呂があることで人気の銭湯です。
- 露天の黒湯を楽しめる珍しい銭湯
- 湯上がりの楽しみとして、「銭湯グルメ」が充実
ふじおくんは、「黒湯に入った後は、シャワーで体を流すのがポイント」と説明。黒湯の成分が肌に残ることで美肌効果が期待できるため、適度に洗い流すことが大切だそうです。
- 桜館の名物「醤油ラーメン」を堪能
- 銭湯の食堂で味わうラーメンは、風呂上がりにぴったり
- シンプルながらも、あっさりとしたスープが特徴で、常連にも人気
また、ふじおくんは、他の銭湯ならではのユニークなグルメについても紹介しました。
- 蒲田福の湯では「ピザ」が食べられる
- 銭湯専用のカードがある銭湯も
- 明神湯は、テレビドラマの舞台として使われたことも
蒲田福の湯のピザは、通常の銭湯とは一味違う楽しみ方ができると話題です。また、銭湯のカードは、回数券のようなもので、地元の常連客に愛用されています。
最後に、ふじおくんと澤部さんは、銭湯文化がこれからも長く続いてほしいと語りました。都内でも減少傾向にある銭湯ですが、こうして個性豊かな銭湯が残っている地域では、まだまだその魅力が健在です。今回の銭湯巡りを通して、レトロ銭湯の奥深さと、その文化の大切さを再認識することができました。
まとめ
今回の「博士ちゃん」は、昭和の名ビルとレトロ銭湯の魅力を深く掘り下げた内容でした。六本木エリアの再開発で姿を消してしまう名ビルを巡りながら、昭和・平成の街並みの変遷を実感。一方、大田区のレトロ銭湯巡りでは、昔ながらの文化が今も息づいていることを知ることができました。これからも、こうした貴重な建築や文化を大切にしていきたいですね。

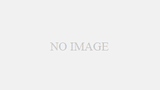

コメント